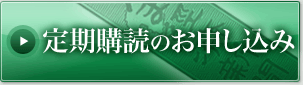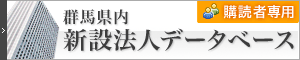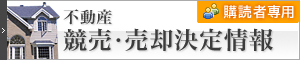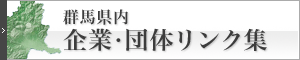【成功させよう「群馬デスティネーションキャンペーン」第12回】
【成功させよう「群馬デスティネーションキャンペーン」第12回】
今から200年ほど前の文化・文政年間、大間々の本町通りの中央には堀が流れ、街区の境には常夜灯が設置され、夜は水路にほのかな明かりが揺れて映っていた。
時は流れて明治10年、本町通りの堀が埋められることになり、街に明かりを灯し続けた常夜灯はその役目を終え、それぞれ別のところへ移設された。それからさらに133年のときが流れた。平成22年3月、3基の常夜灯は「地域おこしのシンボル」という新たな役目を担って里帰りを果たした。この常夜灯の台座には200年前に浄財を寄進した商人たちの名前が刻まれている。そして、その商人たちの子孫の多くが今回の常夜灯の里帰りに際しても主要な役割りを担ってくれた。
その昔、大間々町は足尾銅山の、銅(あかがね)街道の宿場町として栄え、絹市は関東でも屈指のにぎわいを見せていた。今も大間々町で営業を続けている奥村酒造と醤油醸造の岡直三郎商店は2百数十年前に琵琶湖のほとりからやってきた近江商人である。江戸時代、大間々町には6軒の近江商人が酒や醤油の醸造業を営み、『三方良し』(売り手よし、買い手よし、世間よし)という近江商人の商いの精神は大間々町の商業の歴史と文化に大きな影響を与えてくれた。
明治28年に起きた大間々の大火では、273戸の家屋と23棟の土蔵、町役場、警察署、銀行、小学校が燃えたという記録が残っている。当時から岡直三郎商店の仕込み蔵には7000リットルの醤油を貯蔵する木桶が100本以上あった。2丁目、3丁目、4丁目の半分を焼き尽くした火事を消し止めるために大切な商品を惜しげもなく蔵から出し、街並みの半分を火事から救った岡商店の功績は「世間よし」の精神の象徴として今も大間々町の商店街に語り継がれている。
来年はデスティネーションキャンペーンとして群馬の観光地が日本中に紹介される。これを機に、みどり市でも観光資源の掘り起こしやボランティアガイドの充実を図っている。
幸いにも大間々は、わたらせ渓谷鐵道のトロッコ列車の始発駅として全国に知られ、大間々駅を中心とした半径500メートルの範囲には高津戸峡、ながめ余興場という観光スポットがあり、未公開の土蔵の蔵が30棟、2軒の造り酒屋と醤油醸造工場、大間々博物館や常夜灯などが集積しており観光資源は申し分ない。これらの資源に光を当て、町民ひとりひとりが「おもてなしの心のともし火」を掲げて来訪者を温かく迎えることは、大間々町の伝統を守ることでもあり、この町を築いてくれた先祖たちの努力に報いることにもなると思っている。

Last 5 posts in 成功させよう群馬DC
- 第61回「からくり人形芝居」【桐生からくり人形芝居保存会会長 竹田賢一】 - July 2nd, 2011
- 第60回「ふじおかの夏」【藤岡市商工観光課観光係係長代理 梅原拓】 - June 25th, 2011
- 第59回「いせさきもんじゃ」と10年目【伊勢崎商工会議所青年部第23代会長 吉田勝昭】 - June 17th, 2011
- 第58回「私達の群馬DCへの取り組み」【中之条観光ガイドボランティンアセンター代表理事 湯浅昌雄】 - June 11th, 2011
- 第57回「来らっしゃい 花の郷・片品村へ」【片品村観光協会 副会長・尾瀬山小屋組合 会長 関根進】 - June 4th, 2011